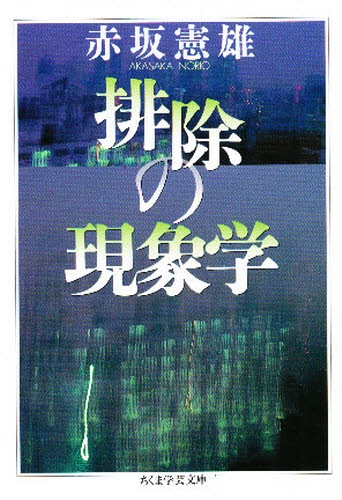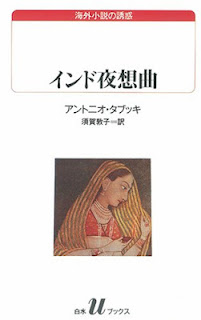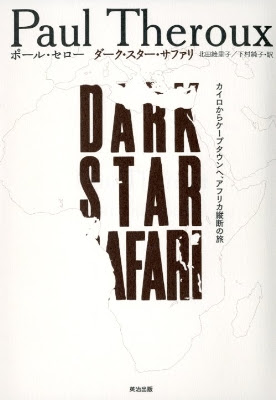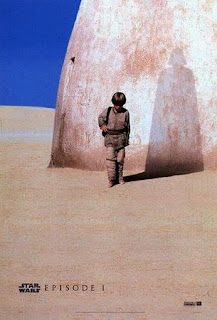テロリズムとデモンストレーション 『風流夢譚』『天皇の逝く国で』『ショックドクトリン』

木下恵助と今村昌平によって2度映画化された『楢山節考』の原作者、深沢七郎はある日、夢を見た。 夢では、東京で大規模な民衆蜂起がおこっている。一部クーデターの気配もあるという。警察と自衛隊が内部分裂し、武力衝突が起こっているそうだ。 街中が騒然とするなか、深沢は民衆の流れにのって皇居へ行く。皇居では革命軍が皇后陛下を取り囲んでいる。夢のなかの深沢はなぜか「このクソババア」などといいながら皇后陛下と取っ組み合いのケンカをする。そして正直者の深沢七郎は、そのあと夢の中でおこる恐るべき出来事を彼のエッセー『風流夢譚』に記載する。深沢とのケンカのあと、斬首された皇后陛下の頭部がぽろりと地面に落下したというのである。 これが雑誌「中央公論」に掲載された直後から、激怒した右翼が深沢七郎宅や中央公論社に街宣車でおしかけるようになる。深沢は警察に保護されて住居を転々とし、長らく放浪生活をおくったといわれている。 翌1961年2月、大日本愛国党の17才の党員が中央公論社社長の嶋中氏の自宅に押しかけて、不在であった嶋中の代わりに妻を刺し、さらにそのとき家にいた家政婦の女性を刺し殺すという事件が起こった。 しかし、問題にしたいのはこの後である。右翼によるテロリズムの被害者であるはずの中央公論と嶋中社長が、中央公論の名によって全国の新聞に「謝罪広告」を掲載したのである。無関係な人間が殺され社長夫人が重傷を負わされた側が、国民に対して謝罪をするというのである。さらに、それが日本の言論出版を担うかの「中央公論」という知の巨人であったことに、当時の知識人らはおおいに驚き、絶望したのである。『風流夢譚』はたしかに軽率で不敬なのかもしれなかった。しかし最後まで戦うと思われていた出版人が、威嚇行為とテロリズムにたいして憲法で保障された権利をあっさりと投げ捨て、謝罪までしてしまうのであれば、いったい誰が言論を守るというのか、と。 1988年12月7日、長崎市定例市議会で、共産党議員が市長に質問をした。「天皇陛下に戦争責任はあるとお考えですか?」。それにたいして市長3期目をつとめる本島等市長(当時)は、一部条件をつけながらも「天皇陛下に戦争責任はある」と回答した。 折りしも昭和天皇が病院で吐血と下血をくりかえし、日本各地に「す