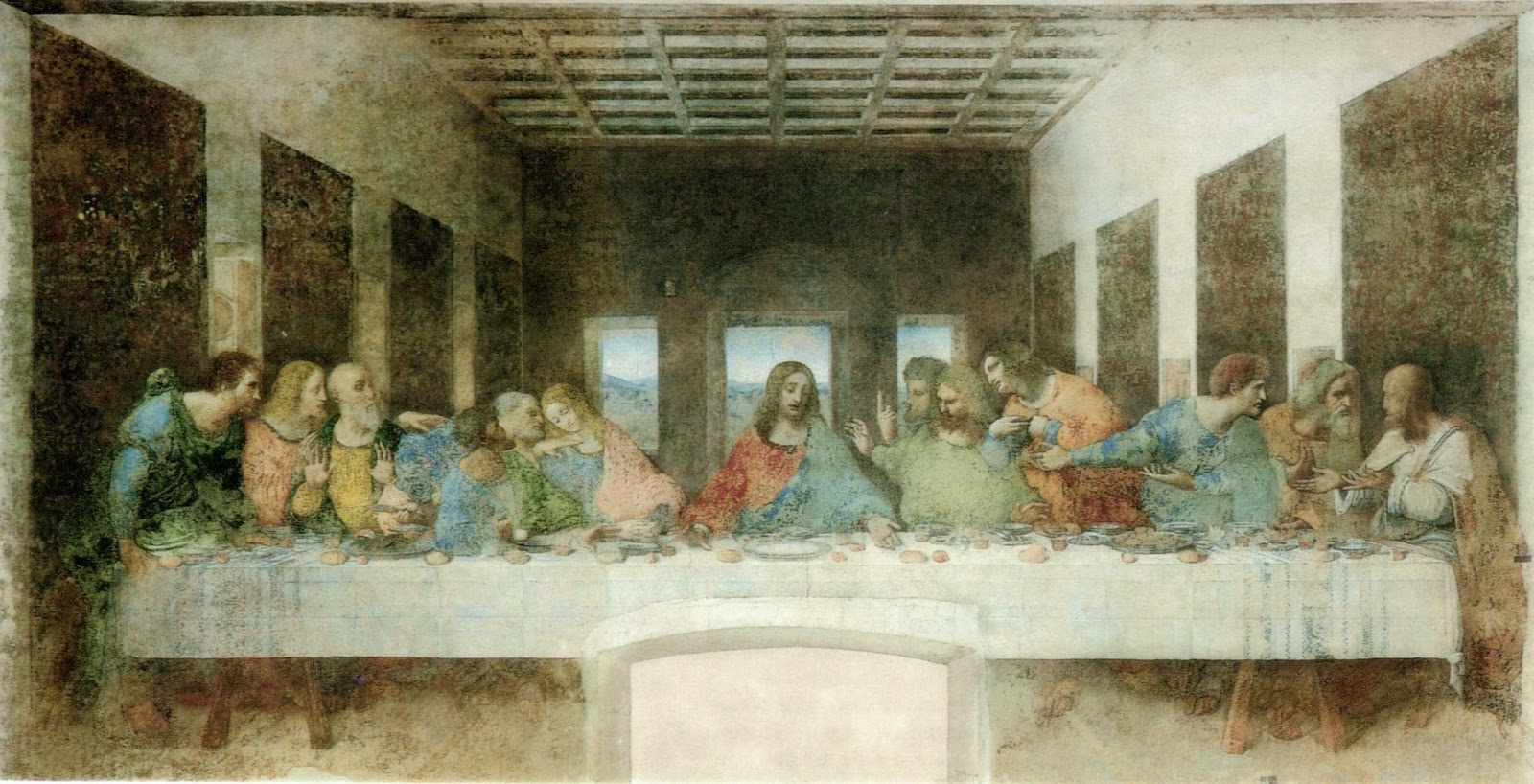『他者の苦しみへの責任』と『闇の奥』

フランシス・フォード・コッポラの名作『地獄の黙示録』の撮影が災難続きであったのは有名な話だ。まず、巨大ハリケーンに一度ならず機材のほとんどを壊される。フィリピン軍に借りる約束だったヘリコプターや爆撃機が、実戦出動のため撮影直前になんどもドタキャンされる。ハーヴェイ・カイテルの代打として選ばれた主演のマーティン・シーンは心臓発作で倒れ、デニス・ホッパーはドラッグで立ち上がることさえできない。あげくのはてにカーツ大佐役のマーロン・ブランドは、痩せるという契約を反故にしただけでなく、さらにでぶでぶに太った体でやってきて、原作はおろか脚本させ読まず、あらゆる演技を拒否したという。借金はみるみる増え、当初17週の予定だった撮影期間は61週にまで延びた。(立花隆『解読「地獄の黙示録」』) そんなあってはならないはずの現場を、コッポラの妻エレノアが撮影していた。それが『ハート・オブ・ダークネス』というドキュメンタリーである。この映画をみると、エレノアが「本気でマーティン・シーンに殺されると思った」と語るほど、想像以上にすさまじい現場であったことがよくわかる。ブランドのスノッブで白々しい「黙示録」のラストや、ドキュメント後半ほとんど発狂状態のコッポラをみていると、むしろこっちの方が現実的な「地獄」なのでは、と思ってしまう。 このタイトルの『ハート・オブ・ダークネス』、日本語訳にすると「闇の奥」となる。『地獄の黙示録』の原作で、ジョセフ・コンラッドの小説『闇の奥』のことである。 コンラッドの小説『闇の奥』の舞台はアフリカ西岸の現コンゴ共和国である。物語の当時、コンゴ共和国はコンゴ自由国という呼び名の、ベルギー王レオポルド2世の私有植民地であった。 1889年にジョン・ダンロップというイギリス人が発明した空気入りゴムタイヤは、その4年前にダイムラーとベンツが発明したガソリン自動車の生産とあいまって爆発的な普及をみせる。とうぜん原料となるゴムが不足する。宗主国ベルギーの80倍の広さをもつコンゴの熱帯雨林には、原料となるゴムの木がほとんど無限のように自生していた。しかもそれを伐採する労働力はタダである。だからコンゴ川沿いにはいくつもの出張所がつくられ、アフリカ大陸のほぼ中央に位置するボヨマ滝あたりまで奥地出張所があったそうだ。(藤永茂著『「闇の奥」の奥』) 『闇の奥』もその