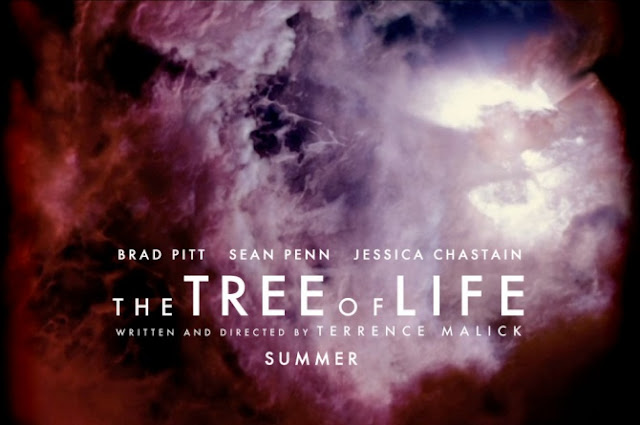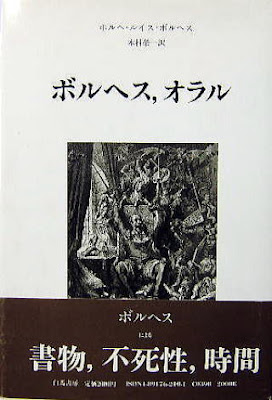東北とは、東北復興とはなにか? 赤坂憲雄『東北学』柳田国男『雪国の春』

青森県の下北半島を旅すると、夏でも寂寞としたその風景にぞっとすることがある。そこはわれわれの見なれた日本の風景ではない、どこか異界めいた違和感をあたえる「田舎」なのである。この違和感がなにかずっと気になっていたが、赤坂憲雄の『東北学』を読んで気がついた。下北にはわれわれ日本人がみなれた水田がないのである。平地や山間といったあるべき場所に水田がないだけで、風景がとつじょ異界じみて見えてくるほどにわれわれ日本人は稲作文化にどっぷりとつかっている。だからおなじ日本であるのに、水田のない下北半島は「異界」であり、「寂寞」とした親しみのないものになってしまう。 それぐらい、稲作文化は日本人の意識形成や価値観に影響をあたえ、いまや稲作のない日本や日本人は考えることさえできない状態にさえなっている。「日本人とは米である」と言ったってだれも反対する人はいないだろう。 そういう「米の国」を根柢でささえるのが、日本の穀倉とも言える東北地方である。「東北」ときいて最初に思い出すのが「米、水田、稲作」という人もおおかろう。 柳田国男が『雪国の春』で書いたのもそのような稲作文化圏の東北である。軒先まで雪に埋もれる東北だからこそ、その雪解けをよろこぶ風習のひとつひとつに稲作文化、つまり「瑞穂の国」の「常民」の姿がある、と書いたのだ。 赤坂憲雄は自著『東北学』において柳田民俗学のこの「常民思想」を批判的に展開するのである。柳田が言うように、ほんとうに日本は「瑞穂の国」という観念で統一的に論じることのできる土地だったのだろうか。 そもそも東北の別名「みちのく」は、畿内からみて海道と山道のつきる果ての「道の奥」という意味である。古代ヤマト朝廷の覇権の及ばぬところという意味である。 中央集権体制に移行しつつあった畿内ヤマト朝廷は、律令制が制定された7世紀頃からすでにこの「みちのく」へおおくの兵をおくっている。そのころの東北は「まつろわぬ民」であり、「蝦夷(えみし)」の国であり、完全に外国であった。 平安初期になると桓武天皇が3度、蝦夷征討をしており、かの坂上田村麻呂が征夷大将軍となって胆沢(現在の奥州市)のアテルイをようやく平定する。アテルイにかんする書物は『続日本紀』ぐらいしか記録がのこっていないようだが、寡兵で大伴弟麻呂を破るなどそうとうな蝦夷の武将であ...