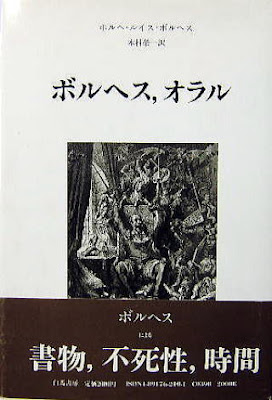書かれたものは残り言われた言葉は飛び去る 『ボルヘス、オラル』『遠野物語』『平家物語』『千夜一夜物語』
人から聞いた話をまただれかにつたえるとき、最初の人の言い回しはほとんど無視される。話の筋や物語やオチが重要であって、筋をつたえるための語彙の選択やレトリックはこのさい関係ない。「山のようにおおきな鬼の影が、村をすっぽり包み込んでしまった」という話も、ひどい場合は「でっかい鬼が村にきた」とつたえても厳密にまちがいではない。まして訂正させられたり立たされたりするわけもない。なぜなら話者がもとにしているのは、文字ではなく話し言葉、耳から入る口頭の情報だからである。
ここが書き言葉(リテラシー)と話し言葉(オーラリティー)の違いである。
ピタゴラスは膨大な数学的・物理学的・哲学的発見をしておきながら、一切文字に書き記すことをしなかった。はじめからピタゴラスは文字の効用を信じていなかったのだ。ピタゴラス教団においてすべては、口頭による伝承だけで受け継がれたのである。
そこにかの有名な言葉が生まれるようになった。ピタゴラス教団の師と弟子が議論をするとき、彼らは最後にこういうのである。「Magister dixit(師曰く)」。
これは議論の終了を意味する符丁でもあり、ピタゴラスという師の考えを反復する行為でもあり、実証的に正しいものを優先することでより真理に近づこうとする理論でもあった。ピタゴラス教団がかなりカルト的で謎めいていたこともあって、「ピタゴラスが言ったんだからそれ以上議論するべきではない」という妄信的な言葉であると思われていることが多いが、実際は真実だと決定できた事柄を同心円としてさらに論理を発展させるためのオープンエンドの言葉なのである。
ボルヘスは「知の伝承、伝達の絶対的条件は、それが書かれないことにある」と書いている。
われわれはつねにその逆を信じている。書かれたものは残り、話された言葉は飛び去るのだと。
「書かれたものは残り言われた言葉は飛び去る」というが、ボルヘスが言うように、ここでいう「残る」というのは、それは死んでしまった屍であるということだ。(ボルヘス『ボルヘス、オラル』)
いきている言葉だけが生き続けるということである。
活字として世に出ることで、遠野で話されていた民話はそこで死亡したといっていいだろう。なぜなら口承文化である民話が固定化され世間に認知されるということは、書かれた『遠野物語』の内容が絶対的正解であって、それ以外のレトリックや言葉遣いは「まちがえ」であるということになってしまうからである。書き留められ出版された以上、それ以上の進化はゆるされないのである。厳格なテクストとして本があるのなら、聞く側も音読の教師のような厳格さをもつべきだと人はかんがえてしまう。
1910年をもって東北の民話は死して屍になったのである。民俗学という学問の貴重で価値あるホルマリンサンプルとなってしまったのだ。
「書かれたものは残り言われた言葉は飛び去る」とはそういう意味である。「残る」とはもう動かないということ、「飛び去る」とは聞き手にその意味が広がっていくということである。
「イリアス」と「オデュッセイア」がほんとうにホメーロスという人物の作品だったのかどうか不明であるように、日本の平家物語の作者がだれなのかも正確にはわかっていない。吉田兼好は、漢詩に長けたといわれる後鳥羽院時代の信濃前司行長が作者ではないかと言っている(『徒然草』)。たしかに平家物語には下野前司行長という名の公家が登場する。これが作者の分身だというのだ。
かりに信濃前司行長が作者だとしても、行長の書いたテクストはとうぜんのこっていない。吉田兼好がそう推論するぐらいなのだから、13世紀にはすでに証拠となるようなテクストや資料はすでになかったのだろう。
吉田兼好は信濃前司行長説につづけて、「行長入道平家物語を作りて、生佛といひける盲目に教へて語らせけり」と書いている。
普通に考えれば、平家物語にテクストはなく、なんらからのかたちで直接、琵琶法師に伝えられたと考えた方が合理的だろう。要は口承の物語である。だからホメーロスのように、平家物語もそのときどきによって微妙に内容をかえていったのである。つまり不安定で確実性の少ないオーラリティーであるかぎり、平家物語は場所と時間によってつねに変化しつづけていたのである。それが固定化されたのは、印刷技術が日本でも一般化された近代になってからである。もっと具体的にいうと、かの岩波文庫に入ることで、800年の末、ようやく平家物語は固定化されたのだ。
現代の日本のわれわれが「千夜一夜物語」を買ってきて読む時、それはたいがいイギリスの軍人でもあったバートンが英語に翻訳したものを底本とするいわゆる「バートン版」である。バートンは、1700年頃もっとも早くに「千夜一夜物語」をヨーロッパ世界に紹介したフランスの東洋学者アントワーヌ・ガランのフランス語訳を参考にしたそうだが、そこでふと不思議な事実に気づく。それ以前のシリア写本やトルコ写本などのどの版にも、かの有名な「アラジンと魔法のランプ」のお話が載っていないのである。ガランの版に突然あらわれる微妙に西洋風の整然としたこの物語は、それ故ガランの創作であったのではないかという研究者もいる。
「あれほど多くの物語を翻訳したあとで、ひとつ作ってみたくなり、実際そうしたということだって大いにありうるのです」とボルヘスは語る。(『七つの夜』千一夜物語)
その他大勢の無名の作者のように、ガランがそのなかのひとりになってはいけないというきまりはないはずである。事実、そのようにして「千夜一夜物語」は成長してきたのである。
版の多さと複雑な入れ子構造の物語などが邪魔をして、人類はだれもが納得できる決定稿を編纂するところまで「千夜一夜物語」の息の根を止められていない。18世紀においてまた新しい物語をうみだすほどの勢いをもってさえいるのである。しかし今後さらに写本が発見され、研究によって理論的な編纂が可能となり、文化史的に納得できる版が世界中で書籍として流通されるようになれば、あの気高く謎めいた名著もいずれ屍となるだろう。
われわれはたかだか600年ほど前に生まれた印刷技術の驚異に畏怖しているのである。知識というものがかたちをもつことに、そこに知識の魂をみているのである。グーテンベルグが一番最初に印刷したものは42行に整えられた聖書であった。神がかたちとなり、重みをもったのである。その権威に恐れおののいたまま、われわれは21世紀にいきている。マラルメは言う。
「印刷された紙を折りたたむということは、ほとんど宗教的といえる行為である。だがそれ以上にすばらしいのは、紙の積み重ねが厚みを持つことで、まさに魂の小さな墓標をかたちづくることである・・・。」
マラルメは書かれた言葉が死体であると気づいていたのであろうか。しかし書かれたものが墓標になるのではない。書かれることで物語は固定化され窒息するのである。
だから小学校の先生は罰さえあたえて読み間違いを防ごうとする。そこに書かれた物語が死体であるからこそ、死者に敬意を表して読みまちがえを許さないのであろう。そのような死者への尊厳だけが、語り継がれた物語へのレクイエムになりえるのだとわれわれはどこかで考えているのかもしれない。
.