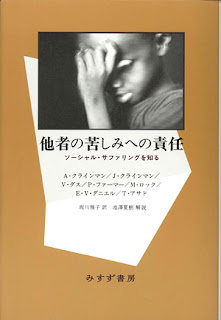脳死について 『他者の苦しみへの責任』
南アフリカでの世界初の心臓移植手術がおこなわれた直後の1968年に、日本で最初の心臓移植手術が札幌医科大学の和田医師により実施された。世界で30例目、移植手術としても日本で2例目という早さだった。心臓に多弁障害をもつ18才のレシピエント(臓器受領者)は、術後半月は順調に回復したのだが徐々に衰弱し、手術から2ヶ月半後に血清肝炎が原因となり呼吸不全で死亡する。
もともと疑惑の多かったこの手術は、レシピエントが死んだことでいっきょに問題を噴出させることになる。センシティブな問題なので思い切ったことは書けないのだが、1991年にはじまったこの事件の調査委員会の報告では以下のような疑惑があり、事件にかんするほとんどの日本人の記憶もこのようなイメージを持っていたのではないだろうか。
まず、18才のレシピエントは心臓移植を必要とする多弁障害ではなかったのではないか。それは和田医師がかつて発明した「ワダ弁」といわれる人工弁で治癒できる心臓病であったのではないか、というものである。そもそもレシピエントはこの人工弁置換手術のために和田医師のいる札幌医科大に入院していたはずであったが、そのことはどこにも発表されずに移植がおこなわれた。
つぎにドナーである21才の溺水した大学生が、ほんとうに脳死状態であったのかどうかの判定があやふやなまま和田医師らにより「脳死宣告」されていたということ。当時はいまのような、二度にわたっておこなわれる脳死判定終了まで移植医はドナーに近づくことも禁じるというような厳格なルールがまったくなかった。脳死判定をするものと、移植手術をする医師がおなじ人間であった。
札幌医科大に搬入されたドナーに筋肉弛緩注射をする和田医師に、抗議した麻酔医が手術室からの退出を命じられたとする証言も疑惑をさらに深めた。
さらには、レシピエントの死後その心臓が3ヶ月にわたって行方不明となり、発見されたときには各部がばらばらに切断された状態になっており、充分な検死もないまま荼毘に付された死体とあいまって、もはやレシピエントの元の心臓がほんとうに移植手術が必要であったのかの検証ができる状態ではなかったという事実もある。
その後、和田医師は殺人罪で起訴され、4年の論争のすえ証拠不十分で不起訴となった。
当時おなじ札幌医科大の整形外科医であった作家の渡辺淳一は、この事件を取材し『白い宴』という小説を発表している。不起訴となった事件だが、ご興味のある方は一読されたし。
しかし移植手術による事件はこれで終わらなかった。その後、筑波大学で実施された腎臓・すい臓移植手術では、ドナーが入院中に精神障害を発症していたという事実が手術後にわかり、またその家族のだれも臓器提供の許可をしていないと証言するというような事件があった。
つまり、そもそものはじめから日本の臓器移植は、生命をないがしろにする野蛮で高慢な医師の「医療実験」といったイメージからはじまってしまったのだ。
医療社会学者・文化人類学者のマーガレット・ロックの、北米と日本での脳死論争の違いから「苦しみ」の変質を論じた『「苦しみ」の転換ーー北米と日本における死の再構築』(『他者の苦しみへの責任』所収)によれば、1990年の心臓移植手術は、アメリカの2000件にたいして日本では0件であるということだ。日本が高度医療技術をアメリカにおおく輸出する立場であることや、日本もアメリカとおなじく医療と宗教が切り離されており、合理的思考を尊び、近代的社会であることを考えると、その違いは文化の違いに根ざすものだという。
ロックは最初の心臓移植手術である「和田心臓移植事件」以降の日本の脳死にたいする動きを追う。
1985年に厚生省「脳死に関する研究班」が、同年「生命倫理研究議員連盟」がそれぞれ脳死にかんする報告書を提出する。そのどちらもが「脳死は人の死ではない」と明言したものであった。
日本医師会は1988年に「脳死は人の死」として定義し、たいして日本精神神経学会は身体障害者の死をはやめる可能性があること、脳機能の不可逆的停止状態を客観的に測定するのは不可能であるとして反対する。
「患者の権利検討会」という一部の医師がたちあげた組織は、脳死患者からのいくつかの臓器摘出が殺人であったという訴訟をおこすが、検察庁は「人の死とは何かという国民的合意がえられていない」という理由で審理却下をしている。エリック・フェルドマンはこの告訴が7年ものあいだペンディングされている状態が、移植手術そのものにたいする躊躇となっていると述べている。
脳死にかんする意見がわかれることを懸念した日本政府は、1989年に「臨時脳死及び臓器移植調査会(脳死臨調)」を設置し、3年後の1992年に数々の条件と少数意見の併記つきで最終答案を提出した。それによると「脳死は人の死」であることを認め、厚生省が定めた脳死基準を妥当なものとして採用するということであった。
その翌日には、法務省、警察庁、検察庁が脳死の容認には反対であるむねの声明を発表し、日弁連は「生命の尊厳」や「医学実験」、あるいは遺産相続への問題が発生する可能性への懸念を表明した。
臓器移植推進派の医師でさえ、和田事件が日本の臓器移植を40年遅らせたと考えるものがおおい。それがほんとに「自己顕示欲のつよい医者の暴走」というひとことで片付けられるものだったのかどうかはわからない。すくなくとも「医者の暴走」という言葉だけでは不十分なのは確実である。臓器移植「技術」がおくれたことは否めないとしても、そこにはふたつの矛盾もある。第一に、かりに最初の移植手術が成功していた場合、議論もなく脳死が人の死であるという既成事実が定着してしまう可能性があるということ。第二に、脳死が人の死ではないという結論がだされていたとしたら、どのみち臓器移植はこの国では実施できなかったということである。人の命を軽んじたという意味ではまちがいないこの事件も、ここまで日本人のもつ倫理観や道徳体系の存在と意義にたいする再考をうながしたということには、なんらかの意味があったのだろうと考える。脳死は医学の問題をこえて、われわれ日本人の文化的成り立ちをするどく問うているのだ。
マーガレット・ロックの論文はその問題をもとりあげている。ロックは、和田心臓移植事件にかかわらず、日本人が脳死を肯定しない理由を、その儒教精神や、先祖供養、運命論、霊魂の不滅、死者の尊厳、神道、アニミズム、贈答文化、近親社会、不自然への不信、文化と自然との融合、といった日本独特の道徳体系や価値観を列挙しながらも、そのもっとも重要な問題として、「日本の進歩的思想家たちが直面している問題」は、個人の自律性や権利など「西洋」の価値観にただ追従するような議論に頼らずに、「保護的な家父長制的思想ーー儒教に由来する保守的な思想ーーの残滓をいかにして取り除くか」という日本人の文化的アイデンティティの問題であり、そのような状況のなかで脳死の議論がされているということだと指摘する。
マーガレット・ロックの論文はその問題をもとりあげている。ロックは、和田心臓移植事件にかかわらず、日本人が脳死を肯定しない理由を、その儒教精神や、先祖供養、運命論、霊魂の不滅、死者の尊厳、神道、アニミズム、贈答文化、近親社会、不自然への不信、文化と自然との融合、といった日本独特の道徳体系や価値観を列挙しながらも、そのもっとも重要な問題として、「日本の進歩的思想家たちが直面している問題」は、個人の自律性や権利など「西洋」の価値観にただ追従するような議論に頼らずに、「保護的な家父長制的思想ーー儒教に由来する保守的な思想ーーの残滓をいかにして取り除くか」という日本人の文化的アイデンティティの問題であり、そのような状況のなかで脳死の議論がされているということだと指摘する。
総体的に言えることは、ほぼ200年にわたって連綿とつづいてきた日本と西洋にかんする論争が、脳死をめぐっておこなわれているということである。
ここでは書かないが、臓器移植先進国の北米でもさまざまな問題があり、それは一般人の知るところの問題もあれば、「臓器狩り」や「第三世界からの輸入」といった社会問題となるものもあり、オルダス・ハクスリーのいう「進歩の悲劇」といった問題もある。だからアメリカが脳死を認めて臓器移植を慣例化していることがよいことがどうかはわからない。日本では脳死の問題について国を二分するほどの議論があったことはよかったと考えたとしても、その議論がそれ以上遅々としてすすまないことは不幸なことである。毎年少なからぬレシピエントが移植を待ちながら死んでいる現状であることを考えるとなおさらである。
ただ、問題なのは、移植技術や、脳死そのものを生みだした人工呼吸器の発明などのテクノロジーが、以前は「自然」であったものを人工的に征服することで、われわれのテクノロジーへの期待がさらに高まることである。『他者の苦しみへの責任』の序文にアーサー・クラインマンが書いている。
われわれはますます、完全な赤ん坊を産むこと、寿命を延長すること、疾病をなくすことが、手の届くところにあると考えるようになっている。そしてそれができないとき、そこに苦しみが生まれることになる。この傾向は、そのような苦しみが理想の想定にもとづくものであり、問題のある政策や日常的現実に根ざすものではないので、とくに危険である。
医療は、発達すればするほどまたあらたな「征服すべき自然」を発見することになり、征服のためのテクノロジーは、いままで「自然」であったものを人体にとっての「不自然」に変えるという永劫回帰に陥っているのかもしれないし、われわれはそれを「健康」とよんでいるのかもしれないのであった。
.