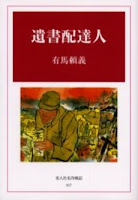消える記憶 『ケルベロス第五の首』と『遺書配達人』
競馬好きの人なら「有馬記念」はとうぜんご存じだろう。これは日本中央競馬会第2代理事長の有馬頼寧の功績をたたえてその名を冠した重賞レースである。有馬頼寧は筑後国久留米藩主の有馬家第15代当主で、近衛内閣で農林大臣をつとめたあと、大政翼賛会設立に参画し初代事務局長を務めている。戦後はA級戦犯として投獄されるが無罪放免となる。有馬家は、今はなき日本の華族であり伯爵である。
その三男が直木賞作家の有馬頼義である。頼義は大臣の父をもつ華族の生活から、A級戦犯告訴による財産差し押さえで一挙に貧窮の生活へ転落し、学生のころから才能を発揮した物書きでなんとかその日暮らしをするが、ようやく1954年に『終身未決囚』で直木賞を受賞する。いっときは「松本清張のライバル」とまで目された有馬だが、いまではもう文庫でさえ手に入らなくなるほど忘れられた作家になってしまったようだ。
その有馬が1960年に出したのが『遺書配達人』である。
昭和19年、主人公の西山民次は北満州へ向かう行軍中、上海において発病し国内送還となる。西山たちがむかう北満州が死地であることは、その小隊すべての男が知っていることだった。生きて故郷に帰れるとはだれひとり想像さえしてなかった。だから幸運にもひとり日本に帰る西山に、のこる13人は自分のもっとも大切な人に宛てて遺書を託すことにする。
帰国後、西山は自分の小隊が北満州で全滅したと聞く。それから、預かった13通の手紙を戦後の混乱のなかで配達するつらい8年間がはじまる。
『遺書配達人』は13の短編がひとつにまとまった連作の形態をとる。西山が配達する遺書の、そのひとつひとつに、遺族の事情があり、世相が反映されており、それぞれの苦悩が書かれている。最後まで息子の帰宅を待ちながら、西山の到着する直前に餓死する母を書いた第一話「墓の女」、戦友の唯一の家族である弟が、預けられた親戚の虐待にたまりかねず放火し死刑となる「焚火」、「約束を果たせなくてすみません。でも弟がいるのがせめてもの救いです」という遺書を、その弟さえ戦争で亡くした開業医の父に届ける「証文」、最後は遺書を書いた本人に手紙を手渡すことになる「受取人なし」まで、小説としては通俗小説だし、いま読むと文体もプロットもかなり「クサい」が、どれもこれもそうとう重いテーマではある。
しかしここで話題にしたいのは、それぞれの短編の冒頭部分に書かれた新聞記事の書き写しである。マッカーサー来日や、戦後の食糧難、東京裁判の様子などの新聞の記事が、遺族を捜す西山のその風景をより具体的にし、当時の情景を浮かび上がらせている。
しかし、西山の配達は、戦後の混乱のため8年もの長い時間がかかる。仕事の合間をぬって、西山が愚直にも遺書を配達しつづけるあいだに、新聞記事は徐々に戦後の色合いを消していき、人々は復興の需要にわきかえり、最後は戦争とは関係のない記事がほぼすべてを占めるようになる。
そこでは、戦争そのものとはまったく違うタイプのつらさを西山は味わう。それは、彼にとっての戦争が、いまだに終わらないというつらさであり、生き残ったことで、かえって世界にとりのこされるさみしさとつらさである。
有馬が書こうとしたのは、もちろん戦争の告発であったろうが、と同時に、戦争が一生癒えぬ傷を一般市民にあたえるという告発でもあり、取り残される悲劇でもあった。
阪神大震災を経験した精神分析医の中井久夫は、新聞の一面にその事件・事故の記事が載らなくなった時が、PTSD発症のタイミングだという。戦争だろうと震災だろうと、とりのこされる恐怖と疎外感は、われわれが思う以上に深刻だという。
このように、個人の記憶がのこったとしても、集合的で社会的な記憶の方が先に消えていくことがある。逆に、そのことはだれひとりおぼえていないのに、社会のなかだけに記憶が息づくこともある。「神話」というものは集合的無意識の記憶装置である。「民話」や「伝説」や「いいつたえ」なども社会のなかに拡散してのこされた組織的な記憶である。もっと広義で考えてよいならば、モラル、規範、道徳、マナーも人類や社会のもつ記憶だろうし、あるいは法律だって記憶の体系化であり条文化であると考えることは可能である。人類が文字という外部記憶装置を発明するずっと前から、集団的に記憶の保存という仕事はなされてきたのだろうし、いまもそうしているにちがいない。
たとえば、1万年以上放射能を出し続ける核の絞りカスを埋めた区域が立ち入り禁止であることを、数万年後の人類に伝えられる言語や方法はないだろうかと、NASAは考えた。この問題についてNASAから研究依頼を受けた言語学者で記号論学者でもあるトマス・シービオクの結論は、「そんな言語や通信手段はない」ということだった。千年もすれば、英語だってラテン語のようにもうだれも話していないかもしれない。アルタミラ洞窟の牛の絵の意味なんてほんとはだれもわからないように、絵文字だってその文化圏の外側の人間には理解できない。つまり、われわれが発明した外部記憶装置は、意外と短期間しか機能しないのである。「もし可能性があるとすれば」とトマス・シービオクはつづける。「これに触ってはいけない」とか「これを食べてはいけない」といったタブーを広めることだ、という。(『もうすぐ死滅するという紙の書物について』ウンベルト・エーコ/ジャン=クロード・カリエール)
集団的記憶が長い時間をかけて神話になるのだが、神話そのものだけが長い時間のこると、過去のわれわれはその意味がわからなくなってくる。もともとはどのような意味がそこにこめられていたのか、ほんとうはどんな事実をつたえたかったのか。
『新しい太陽の書』で有名なアメリカの作家、ジーン・ウルフのSF作品『ケルベロス第五の首』は、そのような消え去った記憶とのこった記憶をテーマにした物語である。
舞台は地球から20光年離れたサント・クロアとサント・アンヌという双子惑星である。サント・クロアは、移民した人類がまるで近世のような独特の文明を築き上げており、文化は退廃し、モラルは薄れ、人身売買が日常的におこなわれており、犯罪が多発している。一方のサント・アンヌは荒野のような大地で、かつては「アボ」とよばれる原住民が住んでいたという伝説がのこる。そのふたつの星を舞台に、3つの独立した物語が語られる。
第1章はサント・クロアの港町ポート・ミミゾンにある娼館「犬の館」にすむ「ぼく」という人物が一人称で語る物語である。犬の館には、「ぼく」以外に、父、弟のデイビッド、叔母のジーニー、家庭教師のミスター・ミリオンが暮らしているが、「ぼく」は弟のデイビッドとミスター・ミリオンとしか会わず、父とはめったに出会うことがなく、叔母は見たこともない。
そんなある日、父によばれ書斎に行くと、父がたずねる。「おまえはなんという名前で呼ばれたい?」。自分の名前を答えるが聞き入れられず、父は「今日からおまえは5号だ」という。その日から毎日のように父の書斎で不思議な薬品を注射され、主人公「ぼく」は次第に記憶を欠損していく。だから第1章は記憶に欠落のある人物が話者の物語である。欠落している部分になにがあったのかは、もちろん読者もわからない。
ある日、叔母のジーニーと偶然であった「ぼく」は、叔母から「ヴェイルの仮説」とよばれるオーブリー・ヴェイル博士の原住民アボに関する理論を聞かされる。それによると、サント・アンヌの原住民は絶滅したのではない。もともと他の生物のすがたを真似る能力のあったアボは、最初の移民船が着陸したときに乗組員全員を虐殺し、そのすがたそっくりに擬態し、その擬態があまりにも完璧だったため、自分がアボであったことも擬態の能力があったことも、いまやすっかり忘れてしまっているのだという。だとすれば、そう話すジーニーも「ぼく」もアボだということになる。
「ぼく」の記憶はますます欠落するようになり、意識のはっきりしない時間がますます多くなる。父の不気味な呪縛から逃げ出すために、とうとう「ぼく」は父殺害を思い立つ。決行の日、地球からきたマーシュという人類学者が「ヴェイル博士に会いたい」と訪ねてくる。驚いたことにヴェイル博士とは、叔母であるジーニーのことであった。最後に、父殺害の現場に居合わせたマーシュ博士が「ぼく」に対して真実を話す。それによると「ぼく」は父の第5世代のクローンであり、叔母ジーニーは第4世代前の父の娘である。家庭教師のミスター・ミリオンは、4世代前の父(つまり「ぼく」)の人格と記憶を納めた「テンナイン」10の9乗のシナプスをもつロボットであること、「ぼく」はクローン技術により数百年の時間をかけて、自己とはなにか、自分とはなんなのかを探求しているのであった。その話を聞いた「ぼく」は、マーシュに対して言う、「あなたは、アボだ」。
第2章はアボのものと思われる古い伝である。双子の兄弟「東風のジョン」と「砂歩きのジョン」は生き別れになり、別々の人生を歩む。砂歩きのジョンは、「沼人」とよばれる部族にさらわれた仲間を助けるために沼人の土地に行くが、逆に囚われてしまう。途中でしりあった「影の子」は、自分たちは遠い星からきた部族だといい、不思議なちからで洪水を起こし、沼人として育った東風のジョンもろとも沼人たちを流し去る。
ちなみに、この伝説を採集したのは、ジョン・V・マーシュ博士であると書かれている。
第3章「V.R.T.」は、マーシュ博士の裁判記録である。どやらマーシュ博士は数年前に「犬の館」で殺人事件を起こしているらしい。しかし本人はどのような罪で起訴され、投獄されているのかまったくわからない。
裁判記録には、マーシュ博士がサント・アンヌでおこなった原住民調査の記録も含まれている。それによると、マーシュ博士は、アボとのハーフと自称する「V.R.T.」という名の少年を助手にして、アボ調査の旅に出る。旅の途中、VRTは夜な夜なだれかと会っているのではないかと、マーシュは思う。その密会が頻繁になるころ、VRTは「川に落ちて死亡した」と手記には記されている。その後、荒野を3年間調査してまわり、手記によるとマーシュは「驚くべき発見」をしてサント・クロアにもどってくる。ヴェイル博士にその発見を伝えるためなのだろう。しかし、その犬の館でマーシュは逮捕される。いったいなんの罪でマーシュは投獄されているのか。そもそもこのマーシュ博士は、アボ調査のために地球を飛び立ったときのマーシュ博士と同一人物なのだろうか。「ぼく」はあれからどうなったのだろうか。VRTは、どうして自分が東風のジョンの末裔だと知っているのだろうか・・・。
記憶は風化する。それは集団的記憶の場合もおなじである。集団的記憶が風化していくと、もともとの意味が変形してしまう。もはや事実のないところに、記録だけがのこることになる。
クローンを重ねることで時間を超越する人格をつくろうとする「ぼく=父」。遠い昔の記憶を人口シナプスに書き込むことで人格を後生に伝えようとするミスター・ミリオン。神話となった人類の起源の記憶。記憶にない罪で投獄されるマーシュ。書かれた文字だけが正確に過去を伝え、書いた本人がもはや本当の本人である保証のないアボの伝説。そうして、記憶の消された人物による一人称の語り。
この『ケルベロス第五の首』は、あまりにも謎が多すぎて、読んでいて辟易する人も多いかもしれない。SFとミステリーという、絶対に組み合わせてはいけないはずの組み合わせをしてしまった作品かもしれない。しかし、記憶と「記憶による自己アイデンティティー」の曖昧さに関する指摘では群を抜いている。
ただ、ボクもこれ以上、この謎だらけの小説をもとに記憶の意味論のようなものを書ける自信はない。なぜなら、この小説を読んだのがもう何年も前で、ボクの記憶も曖昧になりつつあるからであった。
その三男が直木賞作家の有馬頼義である。頼義は大臣の父をもつ華族の生活から、A級戦犯告訴による財産差し押さえで一挙に貧窮の生活へ転落し、学生のころから才能を発揮した物書きでなんとかその日暮らしをするが、ようやく1954年に『終身未決囚』で直木賞を受賞する。いっときは「松本清張のライバル」とまで目された有馬だが、いまではもう文庫でさえ手に入らなくなるほど忘れられた作家になってしまったようだ。
その有馬が1960年に出したのが『遺書配達人』である。
昭和19年、主人公の西山民次は北満州へ向かう行軍中、上海において発病し国内送還となる。西山たちがむかう北満州が死地であることは、その小隊すべての男が知っていることだった。生きて故郷に帰れるとはだれひとり想像さえしてなかった。だから幸運にもひとり日本に帰る西山に、のこる13人は自分のもっとも大切な人に宛てて遺書を託すことにする。
帰国後、西山は自分の小隊が北満州で全滅したと聞く。それから、預かった13通の手紙を戦後の混乱のなかで配達するつらい8年間がはじまる。
『遺書配達人』は13の短編がひとつにまとまった連作の形態をとる。西山が配達する遺書の、そのひとつひとつに、遺族の事情があり、世相が反映されており、それぞれの苦悩が書かれている。最後まで息子の帰宅を待ちながら、西山の到着する直前に餓死する母を書いた第一話「墓の女」、戦友の唯一の家族である弟が、預けられた親戚の虐待にたまりかねず放火し死刑となる「焚火」、「約束を果たせなくてすみません。でも弟がいるのがせめてもの救いです」という遺書を、その弟さえ戦争で亡くした開業医の父に届ける「証文」、最後は遺書を書いた本人に手紙を手渡すことになる「受取人なし」まで、小説としては通俗小説だし、いま読むと文体もプロットもかなり「クサい」が、どれもこれもそうとう重いテーマではある。
しかしここで話題にしたいのは、それぞれの短編の冒頭部分に書かれた新聞記事の書き写しである。マッカーサー来日や、戦後の食糧難、東京裁判の様子などの新聞の記事が、遺族を捜す西山のその風景をより具体的にし、当時の情景を浮かび上がらせている。
しかし、西山の配達は、戦後の混乱のため8年もの長い時間がかかる。仕事の合間をぬって、西山が愚直にも遺書を配達しつづけるあいだに、新聞記事は徐々に戦後の色合いを消していき、人々は復興の需要にわきかえり、最後は戦争とは関係のない記事がほぼすべてを占めるようになる。
そこでは、戦争そのものとはまったく違うタイプのつらさを西山は味わう。それは、彼にとっての戦争が、いまだに終わらないというつらさであり、生き残ったことで、かえって世界にとりのこされるさみしさとつらさである。
有馬が書こうとしたのは、もちろん戦争の告発であったろうが、と同時に、戦争が一生癒えぬ傷を一般市民にあたえるという告発でもあり、取り残される悲劇でもあった。
阪神大震災を経験した精神分析医の中井久夫は、新聞の一面にその事件・事故の記事が載らなくなった時が、PTSD発症のタイミングだという。戦争だろうと震災だろうと、とりのこされる恐怖と疎外感は、われわれが思う以上に深刻だという。
このように、個人の記憶がのこったとしても、集合的で社会的な記憶の方が先に消えていくことがある。逆に、そのことはだれひとりおぼえていないのに、社会のなかだけに記憶が息づくこともある。「神話」というものは集合的無意識の記憶装置である。「民話」や「伝説」や「いいつたえ」なども社会のなかに拡散してのこされた組織的な記憶である。もっと広義で考えてよいならば、モラル、規範、道徳、マナーも人類や社会のもつ記憶だろうし、あるいは法律だって記憶の体系化であり条文化であると考えることは可能である。人類が文字という外部記憶装置を発明するずっと前から、集団的に記憶の保存という仕事はなされてきたのだろうし、いまもそうしているにちがいない。
たとえば、1万年以上放射能を出し続ける核の絞りカスを埋めた区域が立ち入り禁止であることを、数万年後の人類に伝えられる言語や方法はないだろうかと、NASAは考えた。この問題についてNASAから研究依頼を受けた言語学者で記号論学者でもあるトマス・シービオクの結論は、「そんな言語や通信手段はない」ということだった。千年もすれば、英語だってラテン語のようにもうだれも話していないかもしれない。アルタミラ洞窟の牛の絵の意味なんてほんとはだれもわからないように、絵文字だってその文化圏の外側の人間には理解できない。つまり、われわれが発明した外部記憶装置は、意外と短期間しか機能しないのである。「もし可能性があるとすれば」とトマス・シービオクはつづける。「これに触ってはいけない」とか「これを食べてはいけない」といったタブーを広めることだ、という。(『もうすぐ死滅するという紙の書物について』ウンベルト・エーコ/ジャン=クロード・カリエール)
集団的記憶が長い時間をかけて神話になるのだが、神話そのものだけが長い時間のこると、過去のわれわれはその意味がわからなくなってくる。もともとはどのような意味がそこにこめられていたのか、ほんとうはどんな事実をつたえたかったのか。
『新しい太陽の書』で有名なアメリカの作家、ジーン・ウルフのSF作品『ケルベロス第五の首』は、そのような消え去った記憶とのこった記憶をテーマにした物語である。
舞台は地球から20光年離れたサント・クロアとサント・アンヌという双子惑星である。サント・クロアは、移民した人類がまるで近世のような独特の文明を築き上げており、文化は退廃し、モラルは薄れ、人身売買が日常的におこなわれており、犯罪が多発している。一方のサント・アンヌは荒野のような大地で、かつては「アボ」とよばれる原住民が住んでいたという伝説がのこる。そのふたつの星を舞台に、3つの独立した物語が語られる。
第1章はサント・クロアの港町ポート・ミミゾンにある娼館「犬の館」にすむ「ぼく」という人物が一人称で語る物語である。犬の館には、「ぼく」以外に、父、弟のデイビッド、叔母のジーニー、家庭教師のミスター・ミリオンが暮らしているが、「ぼく」は弟のデイビッドとミスター・ミリオンとしか会わず、父とはめったに出会うことがなく、叔母は見たこともない。
そんなある日、父によばれ書斎に行くと、父がたずねる。「おまえはなんという名前で呼ばれたい?」。自分の名前を答えるが聞き入れられず、父は「今日からおまえは5号だ」という。その日から毎日のように父の書斎で不思議な薬品を注射され、主人公「ぼく」は次第に記憶を欠損していく。だから第1章は記憶に欠落のある人物が話者の物語である。欠落している部分になにがあったのかは、もちろん読者もわからない。
ある日、叔母のジーニーと偶然であった「ぼく」は、叔母から「ヴェイルの仮説」とよばれるオーブリー・ヴェイル博士の原住民アボに関する理論を聞かされる。それによると、サント・アンヌの原住民は絶滅したのではない。もともと他の生物のすがたを真似る能力のあったアボは、最初の移民船が着陸したときに乗組員全員を虐殺し、そのすがたそっくりに擬態し、その擬態があまりにも完璧だったため、自分がアボであったことも擬態の能力があったことも、いまやすっかり忘れてしまっているのだという。だとすれば、そう話すジーニーも「ぼく」もアボだということになる。
「ぼく」の記憶はますます欠落するようになり、意識のはっきりしない時間がますます多くなる。父の不気味な呪縛から逃げ出すために、とうとう「ぼく」は父殺害を思い立つ。決行の日、地球からきたマーシュという人類学者が「ヴェイル博士に会いたい」と訪ねてくる。驚いたことにヴェイル博士とは、叔母であるジーニーのことであった。最後に、父殺害の現場に居合わせたマーシュ博士が「ぼく」に対して真実を話す。それによると「ぼく」は父の第5世代のクローンであり、叔母ジーニーは第4世代前の父の娘である。家庭教師のミスター・ミリオンは、4世代前の父(つまり「ぼく」)の人格と記憶を納めた「テンナイン」10の9乗のシナプスをもつロボットであること、「ぼく」はクローン技術により数百年の時間をかけて、自己とはなにか、自分とはなんなのかを探求しているのであった。その話を聞いた「ぼく」は、マーシュに対して言う、「あなたは、アボだ」。
第2章はアボのものと思われる古い伝である。双子の兄弟「東風のジョン」と「砂歩きのジョン」は生き別れになり、別々の人生を歩む。砂歩きのジョンは、「沼人」とよばれる部族にさらわれた仲間を助けるために沼人の土地に行くが、逆に囚われてしまう。途中でしりあった「影の子」は、自分たちは遠い星からきた部族だといい、不思議なちからで洪水を起こし、沼人として育った東風のジョンもろとも沼人たちを流し去る。
ちなみに、この伝説を採集したのは、ジョン・V・マーシュ博士であると書かれている。
第3章「V.R.T.」は、マーシュ博士の裁判記録である。どやらマーシュ博士は数年前に「犬の館」で殺人事件を起こしているらしい。しかし本人はどのような罪で起訴され、投獄されているのかまったくわからない。
裁判記録には、マーシュ博士がサント・アンヌでおこなった原住民調査の記録も含まれている。それによると、マーシュ博士は、アボとのハーフと自称する「V.R.T.」という名の少年を助手にして、アボ調査の旅に出る。旅の途中、VRTは夜な夜なだれかと会っているのではないかと、マーシュは思う。その密会が頻繁になるころ、VRTは「川に落ちて死亡した」と手記には記されている。その後、荒野を3年間調査してまわり、手記によるとマーシュは「驚くべき発見」をしてサント・クロアにもどってくる。ヴェイル博士にその発見を伝えるためなのだろう。しかし、その犬の館でマーシュは逮捕される。いったいなんの罪でマーシュは投獄されているのか。そもそもこのマーシュ博士は、アボ調査のために地球を飛び立ったときのマーシュ博士と同一人物なのだろうか。「ぼく」はあれからどうなったのだろうか。VRTは、どうして自分が東風のジョンの末裔だと知っているのだろうか・・・。
記憶は風化する。それは集団的記憶の場合もおなじである。集団的記憶が風化していくと、もともとの意味が変形してしまう。もはや事実のないところに、記録だけがのこることになる。
クローンを重ねることで時間を超越する人格をつくろうとする「ぼく=父」。遠い昔の記憶を人口シナプスに書き込むことで人格を後生に伝えようとするミスター・ミリオン。神話となった人類の起源の記憶。記憶にない罪で投獄されるマーシュ。書かれた文字だけが正確に過去を伝え、書いた本人がもはや本当の本人である保証のないアボの伝説。そうして、記憶の消された人物による一人称の語り。
この『ケルベロス第五の首』は、あまりにも謎が多すぎて、読んでいて辟易する人も多いかもしれない。SFとミステリーという、絶対に組み合わせてはいけないはずの組み合わせをしてしまった作品かもしれない。しかし、記憶と「記憶による自己アイデンティティー」の曖昧さに関する指摘では群を抜いている。
ただ、ボクもこれ以上、この謎だらけの小説をもとに記憶の意味論のようなものを書ける自信はない。なぜなら、この小説を読んだのがもう何年も前で、ボクの記憶も曖昧になりつつあるからであった。