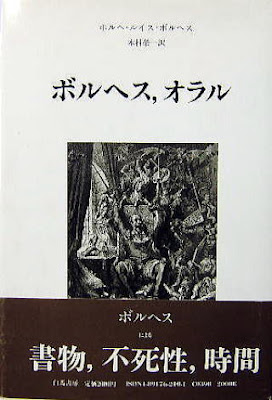小学校のころ音読という国語の授業があった。もちろん今でもある。教科書に書かれた小説や詩を声に出して読むのであるが、これがなかなか厳しいもので、一字一句読みまちがえてはいけないのである。まちがえると、前にもどって訂正しつつ再読させられる。ひどいときなど数回読みまちがえると「立ってなさい!」と罰をうけたりする。なぜこんなに厳しいかというと、音読のもととなっているものが活字のテクストであるからだ。学校教育においては、テクストに書かれたことは絶対なのである。 人から聞いた話をまただれかにつたえるとき、最初の人の言い回しはほとんど無視される。話の筋や物語やオチが重要であって、筋をつたえるための語彙の選択やレトリックはこのさい関係ない。「山のようにおおきな鬼の影が、村をすっぽり包み込んでしまった」という話も、ひどい場合は「でっかい鬼が村にきた」とつたえても厳密にまちがいではない。まして訂正させられたり立たされたりするわけもない。なぜなら話者がもとにしているのは、文字ではなく話し言葉、耳から入る口頭の情報だからである。 ここが書き言葉(リテラシー)と話し言葉(オーラリティー)の違いである。 もともと文学とは口承の芸術であった。いや、文学だけではなく学問とはもともとすべて口頭でおこなわれていた。 ピタゴラスは膨大な数学的・物理学的・哲学的発見をしておきながら、一切文字に書き記すことをしなかった。はじめからピタゴラスは文字の効用を信じていなかったのだ。ピタゴラス教団においてすべては、口頭による伝承だけで受け継がれたのである。 そこにかの有名な言葉が生まれるようになった。ピタゴラス教団の師と弟子が議論をするとき、彼らは最後にこういうのである。「Magister dixit(師曰く)」。 これは議論の終了を意味する符丁でもあり、ピタゴラスという師の考えを反復する行為でもあり、実証的に正しいものを優先することでより真理に近づこうとする理論でもあった。ピタゴラス教団がかなりカルト的で謎めいていたこともあって、「ピタゴラスが言ったんだからそれ以上議論するべきではない」という妄信的な言葉であると思われていることが多いが、実際は真実だと決定できた事柄を同心円としてさらに論理を発展させるためのオープンエンドの言葉なのである。 ボルヘスは「知の伝承、伝達の絶対的...