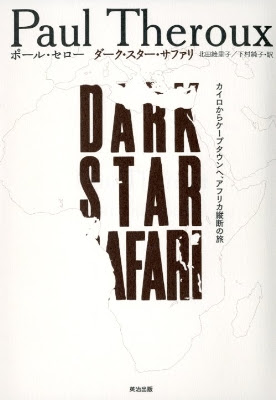うつ病とメランコリア 『メランコリア』ラース・フォン・トリアー

うつ病の人がおおい。厚生労働省の調査結果では日本人のおよそ15人に1人はうつ病だという。うつ病を発症させる因子が社会性ストレスといわれているところから、現代病の一種と考えている人もおおいようだが、そうでもない。増えたのは、この病気が社会的に認知されたからである。 うつ病という名前がなかった昔は、それを「メランコリア」と言っていた。紀元前400年頃すでに、「医学の父」とよばれるヒポクラテスがこの悩ましい病気について言及している。 ヒポクラテスによると、人間には4つの体液があるという。血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の4つの体液が正しい状態にないと、人は病気になるという。これを「四体液説」という。 四体液説を信じている医者はもういないが、それでも体内のバランスが崩れて病気になるという考え方はいまでも通用している。なんのバランスなのか指摘できないのに、やたらとバランスが大事だという人がいるのは、2400年前に流布した四体液説のなごりかもしれない。 その四体液説のうちの黒胆汁が過多になると患うのが、メランコリアである。メランコリアになると悲しみや不安や憂鬱をかんじ、病気が進行すると無気力になり、妄想や幻覚をみることもあるという。つまりいまでいううつ病である。 16世紀初頭の版画家アルブレヒト・デューラーの傑作『メランコリアⅠ』は、まさにこの鬱気質を描いている。 版画の中で、小屋の前に腰かけた翼のある人物が右手にコンパスと本を抱えている。しかし彼女が見ているのは手元の本ではなく、版画の枠外のどこか遠くのようである。足もとには大工道具が転がっており、痩せた犬が寝そべり、不思議な多面体が置かれている。はしごが立てかけられた背後の小屋の壁には、魔方陣が描かれ、鐘、大きな砂時計、はかりがつるされている。背景は波のない海のようであり、上空に虹が架かり、その向こうを巨大な彗星が飛んでいる。 「うつ病」というアカデミックで散文的な用語にはなく、「メランコリア」という言葉には存在する意味に、憂鬱、憂い、思索、悲哀といったものがある。デューラーの『メランコリア』には、そのどれもが含まれているように思える。暗い顔の天使は、うつ病というよりもなにかを憂いているようにも見えるのである。 ヒポクラテスの四体液説は、物質の四大元素(空気・火・水・土)につながっ