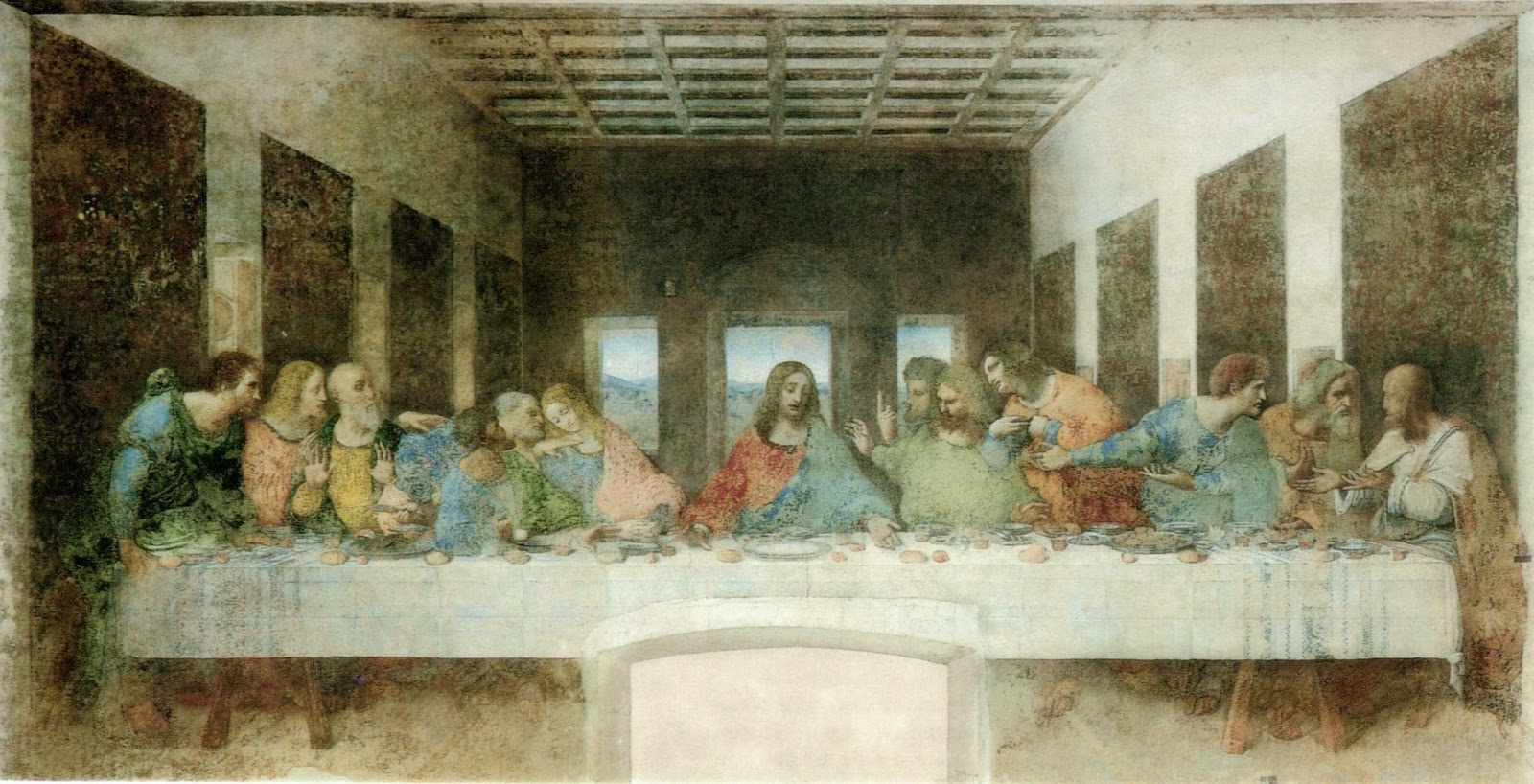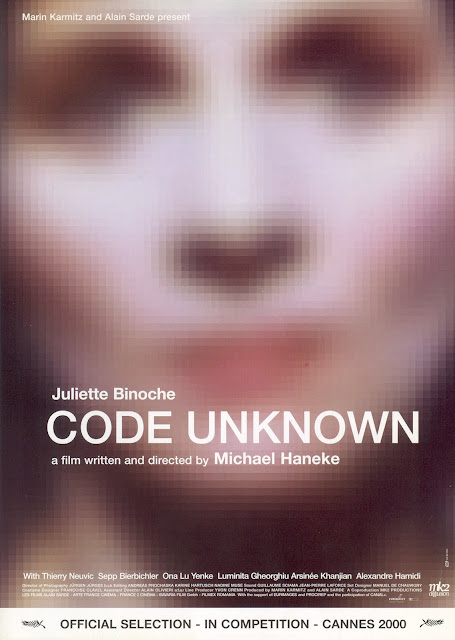『最後の手紙』フレデリック・ワイズマン、『人生と運命』ワシーリー・グロスマン
- 『全貌フレデリック・ワイズマン』
- 『人生と運命』ワシーリー・グロスマン
- 『赤軍記者グロースマン』アントニー ビーヴァー
- 『最後の手紙』フレデリック・ワイズマン
そのテキストこそが、ロシア系ユダヤ人作家ワシーリー・グロスマンの、スターリングラード戦を書いた大長編小説『人生と運命』である。この作品が完成したのは1960年であるが、日本では2012年1月にようやくみすず書房から日本語訳が出版されて話題となった。
その後ワイズマン監督は、フランスの国立劇団コメディー・フランセーズを題材にしたドキュメンタリー(『コメディー・フランセーズ』96年)を撮影したことで劇団の支配人ジャン=ピエール・ミケルと親しくなり、同劇場用になにか演出してみないかと持ちかけられる。ワイズマンは即座にこの台本を提示する。主演には、コメディー・フランセーズの重鎮カトリーヌ・サミーを起用する。
芝居は2000年3月から1ヶ月間上演され、大成功を収めたあとには北米巡業も成功させる。さらにその芝居を映画化すべく、アルテとキャナルプリュスから出資をとりつけ、2003年にニューヨークのフィルムフォーラムで初上映されたそうである。それが、フレデリック・ワイズマンのただ二つしかないフィクション映画のひとつ、『最後の手紙』の由来である。(『全貌フレデリック・ワイズマン アメリカ合衆国を記録する』岩波書店)
『最後の手紙』は上述のロシア人作家ワシーリー・グロスマン『人生と運命』を原作としている。しかし827ページの重厚長大な3部作をすべて映画化しているのではない。第1部第18章のわずか14ページ(日本語版では19ページ)のみを、カトリーヌ・サミーの一人芝居というかたちで映像にしているのである。「手紙の章」とも言われることもあるこの第18章にかんして、フレデリック・ワイズマンは「これまでに読んだもののなかでもっとも的確に、ホロコーストにかんするすべての問題が凝縮されていた」と言っている。
『人生と運命』はユダヤ系ロシア人ワシーリー・グロスマンが、20世紀最大の死闘と言われたスターリングラード攻防戦を背景に、軍人、科学者、農民、医師といったロシアのごく普通の人々が、ナチズムに迫害され捕虜となり絶滅収容所でホロコーストの犠牲にされ、さらには国内のスターリニズムによる圧政とジェノサイドという非人間的な時代を生きる様を、スターリン、ヒットラー、アインヒマン、ベリアといった実在の人物を織り交ぜながら史実に沿って描いた戦争大河小説である。フランスの哲学者でありタルムード学者のエマニュエル・レヴィナスはこの『人生と運命』を「もっとも影響を受けた20世紀の小説」と発言している。フランス「ルモンド」誌は20世紀最大のロシア文学だと言う。
ジャーナリストでもあったグロスマンは、従軍記者としてスターリングラード攻防戦を最前線で体験している。とくにドイツ軍敗走のあと、ポーランド入城に付き従った解放直後のトレブリンカで、彼は世界ではじめてナチス・ドイツのユダヤ人絶滅という途方もない悪を目撃する人間のひとりとなる。
そのあたりの赤軍記者としてのグロスマンのことであれば、白水社『赤軍記者グロースマン 独ソ戦取材ノート1941‐45』に詳しいようだ。特にニュルンベルグ裁判にも証拠として採用されたというトレブリンカ絶滅収容所への入城の記録は、ナチスのホロコーストを世界に知らしめた第一級の資料的価値さえあるだろう。
また、グロスマンの母は故郷ウクライナにおいて、ドイツ占領軍のユダヤ人絶滅計画により殺害されたベルディチェフの2万人の被害者の一人である。
『人生と運命』第18章は、ナチスのユダヤ人ゲットーに入れられた母から息子への最後の手紙として書かれる。つまり、手紙の書き手であるアンナ・セミョーノヴナは、あきらかにグロスマンの母エカテリーナ・サヴェリエヴナ・グロスマンをモデルとしている。
このことについて、ワイズマン監督は「この手紙は二重の意味でラブレターである。母親から息子への、そして、息子から母への。グロスマンが自分の母のためにこれを書いたという前提をもし肯定するならば」とインタビューに答えている。(『全貌フレデリック・ワイズマン アメリカ合衆国を記録する』岩波書店)
『人生と運命』第18章はこのようにしてはじまる。
ヴィーチャ、わたしは前線とは反対側のユダヤ人ゲットーの有刺鉄線の中にいます。でも、この私の手紙がお前に届くものと確信しています。お前の返事を私が手にすることは決してないでしょう。私はいなくなるのです。お前が私の最後の日々について知ってくれることを望みます。知ってくれると思うことで私には、この世を去っていくことがすこし楽になります。
ヴィーチャ、人々を真に理解することは難しいことです……7月7日、ドイツ軍が町に突入してきました。・・・
バルバロッサ作戦のわずか2週間後に陥落したベルディチェフでは、ナチス占領下となるや手のひらをかえしたように反ユダヤ主義に与する人々が書かれる。アンナのもとに隣家の娘がやってきて言う。
「荷物をまとめてちょうだい。わたしあなたの部屋に移るの」
「じゃあわたしはあなたの部屋に移るのね」
「いいえ、あなたは台所の奥の部屋に移るのよ」
部屋の外で声がする。
「ありがたいことに、ユダヤ人は終わりよ」
そういう老女の息子はユダヤ人と結婚しており、いつもその孫娘の話をアンナにしていたというのに。
会うたびに息子のことをほめてくれていた教師が、ナチス侵攻後「これで空気がきれになった」と話していたという噂を聞く。「ニンニク臭がしなくなった」
眼科医として務めていた病院を解雇され、給料の支払いを求めると「スターリンに払ってもらえ」と拒否される。
アンナが部屋に帰ると扉が壊され家具が持ち出されている。抗議をすると、こう宣告される。
「あなたは法の保護の外にいるのよ」
部屋を去り旧市街のゲットーに移る時、残ったアンナの家具を誰がもらうかで隣人同士がアンナの目の前で言い争いをしている。
アンナは息子に書く。
有刺鉄線の中でどういうことを経験したか、ヴィーチェンカ、分かりますか。私は恐怖を感じるだろうと思っていました。しかし想像できますか、この家畜のための囲いの中で私は気持ちが楽になったのです。(…)そしてゲットーでは、私は馬のように車道を歩かないですむのです。敵意のある眼差しもありません。知人たちはまっすぐ私の目を見ますし、私と会うことを避けたりはしません。この囲いの中では、みんながファシストによって押しつけられた印をつけています。ですから、ここではこの印が私の心に焼けるような痛みを与えることがないのです。ここでは私は自分が何らの権利もない家畜ではなく、不幸な人間であると感じました。
その後のゲットーでの極限の生活、「芋掘り」といって連れていかれた若者たちが戻らぬこと、ポーランドから逃げてきた女性が向こうで見聞きした恐怖の噂、楽観主義者ほど強欲になるその姿、そして思ってもみなかった人たちの親切や極限状態でも他人を思いやる人たち・・・。
「スターリンとチャーチルが会談した結果ドイツがユダヤ人の強制連行をやめた」
「ソビエト軍が急激に攻勢に移っている」
といった楽観的な無数の噂が徐々に現実味を失い、人々は「特殊な職能のあるものは殺されないそうだ」といった絶望的な楽観にしかすがることができない。
しかしアンナにははじめからすべてが見えていたのだ。
そして私には、廃墟のそばを通りながら誰かがこう言うのが、とてもはっきりと目に見えたのです。「覚えているかい、ここにはかつてユダヤ人たちが、ペチカ据付工のボールフが住んでいた」。(…)その話し相手はこう言うのです。「ほら、あの梨の老木の下には、いつも女医が腰かけていましたよ。苗字は忘れましたが、彼女のところで目を治療したことがあります。仕事の後に、彼女はいつも籐椅子を持ちだして、本を手に腰かけていましたよ」。そういうことになるでしょう、ヴィーチャ。
そうしてアンナは「ソビエト政権になって忘れていた、私がユダヤ人であるということ」ただそれだけの事実によって殺されるのである。
ジャガイモ掘りに送られたユダヤ人たちが町から4ヴェルスターのロマノフに向かう道沿いの飛行場のそばで長くて深い溝を掘っていることを、私たちは知りました。ヴィーチャ、この場所の名前を覚えておいてくださいね。お前はそこで共同墓地をみつけることになるでしょう。そこにお前のお母さんは眠ることになるでしょう。
数あるナチスのホロコーストを書いたもののなかでこの「手紙の章」が傑出しているのは、ホロコースト全体を書くことで、個々の殺人、個々の生命が暴力によって奪われたという問題を全体性の中にうもれさせていまうという、われわれの犯してしまいがちな過ちを、ほぼ同時代においてみごとに避けているからである。ドイツの哲学者テオドール・アドルノの「アウシュビッツの後では、もはや詩を書くことは野蛮である」という有名な箴言に対してどのような方法論を持ち得るのかという問題である。
第二次世界大戦においてシベリアの強制収容所で過酷な日々をすごした詩人の石原吉郎は「ジェノサイドのもっとも大きな罪は、そのなかの一人の重みを抹殺したことにある。そしてその罪は、ジェノサイドを告発する側も、まったくおなじ次元で犯しているのである」という。(石原吉郎『望郷と海』)
グロスマンは、ソ連領内におけるユダヤ人虐殺の記録『黒書』の編集方針をめぐってこう発言している。
「われわれが所有する資料のすべては、何らかの奇蹟でからくも死を免れた人々による報告である。だが、われわれは大地に横たわり自ら語ることのできない人々の代わりに語る責任も負っている。われわれが光を当てなければならないのは、バービー・ヤールに連れて行かれた99%の人たちの身に起きたことであって、バービー・ヤールから逃れた5人に起きたことではない。」(みすず書房の本棚 パブリッシャーズ・レビュー「二つの全体主義に抗して」赤尾光春)
『人生と運命』の主人公である核物理学者のヴィクトルは、核反応にかんする論文が観念的で「ユダヤ的でさえある」という理由で学会を追われ、人種主義的差別に抗議したことで逮捕が迫る。だが、ヴィクトルの心はすがすがしかった。無意味な懺悔を拒否し、仲間の不当な扱いを糾弾し、彼が考え、正しいと思う良心をまもったからである。
しかしその逮捕の直前、彼のもとにスターリン直々に彼の論文にかんする激励の電話がかかってくる。彼の立場は一夜にして変化し、人々はヴィクトルを褒め称える。だが、そこに待つのはヴィクトルがその拒否を心に誓った核物理学を原子爆弾製造に転用させる技術であり、ヴィクトルが想像だにしなかった学者を、国家の反逆者でありスパイであると告発する学会の署名への圧力と強制であった。
このヴィクトルの姿は、グロスマン自身の写し絵である。『人生と運命』の前編とも言える長編小説『正義の事業のために』の原稿には、全文720ページとほぼ同量の検閲校正が「ノーヴイ・ミール」編集部と参謀本部歴史部により入れられ、5年間絶え間なく修正を受け続けた結果、もとの内容とは別のものに書き換えられてしまうという経験のあと、グロスマンは「プラウダ」編集部において無罪であるとしか思えないユダヤ人医師団を糾弾する文案に署名をもとめられている。(第1部解説「人間からはじめよう…」M・スミノワール)
スターリングラード攻防戦を勝利したことでスターリンの独裁政治はますます弾圧を強め、さらにこの医師団事件をきっかけに国内のユダヤ人をナチスとおなじ理由において殲滅しようとする。
スターリングラード攻防戦を勝利したことでスターリンの独裁政治はますます弾圧を強め、さらにこの医師団事件をきっかけに国内のユダヤ人をナチスとおなじ理由において殲滅しようとする。
このことについてブルガリアの哲学者であり記号論学者であるツヴェタン・トドロフは「グロスマンは、ソヴィエトの第一級の作家が自らの位置を変えた唯一の、最重要の例である」と言う。
ソビエトにおける反ユダヤ主義とナチズムとの類似に気づいたグロスマンは、大著『人生と運命』を書く。しかしグロスマンが書き上げた原稿は密告により、タイプライターやそのインクリボンごとKGBに没収され、フルシチョフへの嘆願は無視され、イデオロギー担当書記のスースロフにより「今後200年間は出版不可」と宣告される。「国外でもよいから出版してほしい」という遺書を残し、グロスマンは失意のまま1964年に死去する。
しかしその後、友人らが隠し持っていた原稿のマイクロフィルムが密かに国外に持ち出され、1980年にスイスにおいて出版される。祖国ソビエトで『人生と運命』が出版されたのは1988年、グロスマンの死後24年たってからであり、ソビエト社会主義共和国連邦崩壊のわずか3年前であった。(「二つの全体主義に抗して」赤尾光春)
詩を書くことさえ野蛮となるこの問題を文字に書くことを成功させた数少ない作品のひとつであり、グロスマン自身の人生がフィクションを史実そのものに変えた奇跡的なこの作品を映像化するという難題を、ワイズマン監督はサミーの一人芝居という極端な演出で見事に成功させている。
風景も小道具もない暗く白い部屋の中に、喪服のような黒い服を着たカトリーヌ・サミーの影が、特殊なライティングによって二重にも三重にも映し出される。まるでそれはアンナ自身の霊であるかのようにも見える。その幽霊が頻繁に出没する暗い部屋で、サミー=アンナは愛する息子への手紙を朗読する。ワイズマンとは思えないような女優のアップと、壁に映る幽霊のような黒い彼女の影と、そうして胸につけたユダヤ人を示す黄色い星が、観客にすでにこの母親がナチスにより殺されていること思い出させる。
ロラン・バルトは写真論『明るい部屋』において「写真は本質的に<それが=かつて=あった>というノエマを持つ」というようなことを書いている。新潟の水俣病を描いた『阿賀に生きる』で有名なドキュメンタリー映画作家、佐藤真はこのことを「写真は潜在的な遺影である」と言い換える。つまり鑑賞者に動画特有のイリュージョン(幻覚)を生み出すことをまるで拒否するかのようなこの『最後の手紙』の演出においては、目の前にいるこの人物が、すでに過去のものであり、その遺影であるという前提をわれわれは持つしかないのである。だから、われわれ観客は必然的にこの手紙を親切な人づてに受けとることになるだろう息子ヴィクトルと似た場所に立たされる。ホロコーストが1通の手紙によってひとりのユダヤ人女性の姿となり、ワイズマンの演出によりその女性はわれわれの母の姿と重なる。観客は「ホロコースト」という言葉さえなかったかつてのベルディチェフや、そしてトレブリンカをかいま見る。
1時間程度の短い映画だが、見終わると、もはやこの演出でしか映像として成立しなかっただろうとしか思えなくなる。おなじくホロコーストを描いて成功した数少ない作品、実験的なコラージュの手法によってそれを成し遂げたアラン・レネの『夜と霧』や、上映時間9時間を超えるインタビュー集によるクロード・ランズマンのドキュメンタリー『ショアー』のように。
人類史上2度目の核難民キャンプとさえ言われる、福島第一原発事故による町ごとの疎開を追ったドキュメンタリー映画『フタバから遠く離れて』の監督、船橋淳がインタビューで「(劇映画である『最後の手紙』は、)あなたのドキュメンタリーが世界の複雑さをそのまま受け止めようと開かれているのに対して対照的だ」と問うたことに対し、ワイズマンはこう答えている。
「最後の手紙のような映画は、一人の女性の目を通して世界を見るものだ」
たったひとりのユダヤ人女性が、後世にとってもっとも重要な事実や歴史を伝えることだってあるだろう。ホロコーストという語で理解してしまえるという傲慢さの中にうもれる、殺された個々の人々の消えて行くしかない無数の言葉を救いだすこれらの作業、グロスマンが「大地に横たわり自ら語ることのできない人々の代わりに語る責任」と言ったこの果てのない仕事は、どのような歴史書の編纂と比べてもその重要さにおいて劣ることはないと、ボクはワイズマンの『最後の手紙』をみて思うのであった。
(敬称略)