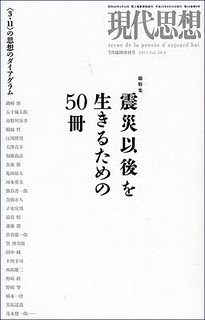ラプンツェル考 『グリム童話集』『ピアニスト』『競売ナンバー49の叫び』

男性優位社会の日本では、女性は「家庭」という箱に閉じ込められているという。家庭の秩序をまもることさえしていればいいという社会の圧力は、おのずと女性から性別を超えた個人の能力や価値観、はては権利と権利の行使の意識さえ徐々に剥奪していくことになるだろう。たしかに、日本の社会がかかえる問題のひとつに、女性から剥奪されるこれらの社会性と、男性側からみた女性の価値基準が齟齬をきたしていることがあげられる。 日本の男性の擁護をするわけでもないし、まして合コンで「得意な料理は肉じゃが」と答える女性にときめく志向もまったくないが、ただ、女性を「閉じ込める」傾向はなにも日本独自のものではない。 『グリム童話集』 古くは1812年にドイツで出版されたいわゆる『グリム童話』に集録されている「ラプンツェル」は、魔女に育てられた髪の長い少女が出入り口のない高い塔に幽閉される物語である。改訂ごとに性的な逸話は削除されていったようだが、1812年の第一版では夜な夜なラプンツェルの髪をつたって塔を這い上がる王子と性交渉をかさね、身重になって以前の服が入らなくなることで魔女に妊娠をさとられ長い髪を切られたうえに高い塔から放逐される物語が描かれている。「ラプンツェル」は、女性と「閉じ込め」が結合したもっとも有名な物語だろう。 その後、王子は魔女にだまされて両目を失明してしまう。何年も荒野を放浪したあと、双子を出産し育てていたラプンツェルの歌声を聞いて巡り会った王子は彼女の涙で視力を回復し、ふたりは幸せに暮らしたという。 改訂で削除されていったとはいえ、「ラプンツェル」には性的な隠喩がおおくふくまれている。そのもっともわかりやすいのがラプンツェルの幽閉されている場所が塔であることだ。上空にむかってそそり立つ塔のイメージは男性器そのままである。幽閉されるなら魔女の住居の地下や納屋でもよさそうだが、そういった空虚ではなくあくまでも人目につきやすい直立建造物そのものを幽閉場所とする設定の無理は、この隠喩の隠された意味の重要性をあらわしているからだ。 しかしここで思いつくのは、このラプンツェルの物語に「父性」を象徴する人物が一切登場しないことである。 『クレオール主義』今福龍太 コロンビア大学のジーン・フランコ教授は、彼女の論文『エスノセントリズムを超えて』のなかで「ラテンアメリ